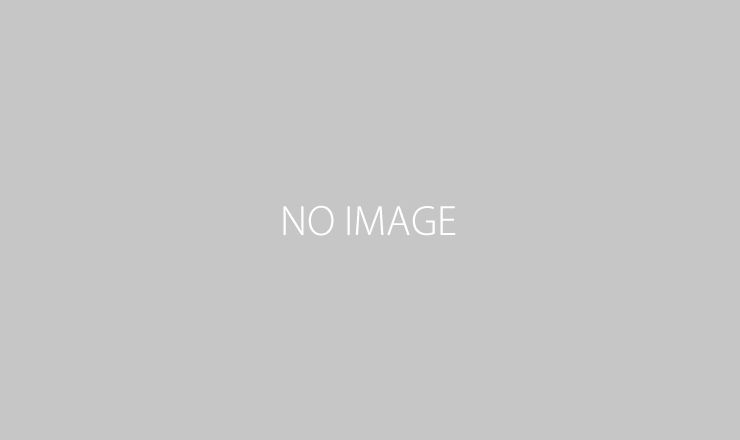
誤情報対策に与える認知バイアスの影響:田中 優子(国立大学法人名古屋工業大学 基礎類 教授)
人は誤情報を容易に信じる一方で,一度受け入れられた誤情報の影響を訂正情報によって事後的に緩和することは容易ではありません。この背後には,複雑な心理的メカニズムが存在します。ソーシャルメディアなどで迅速・広範に拡散する誤情...
応用脳科学アカデミー
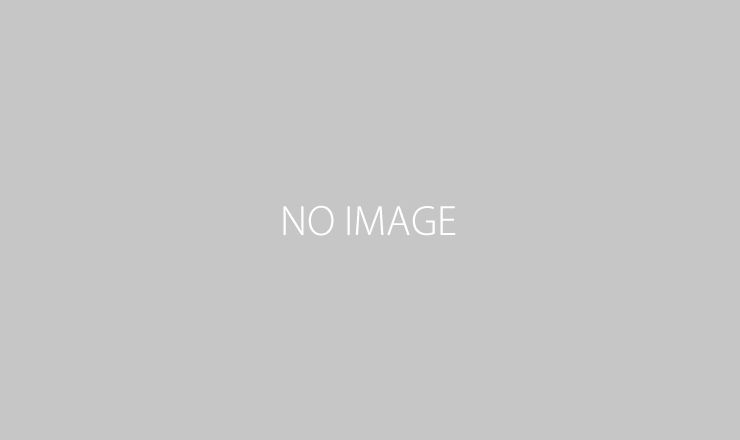
人は誤情報を容易に信じる一方で,一度受け入れられた誤情報の影響を訂正情報によって事後的に緩和することは容易ではありません。この背後には,複雑な心理的メカニズムが存在します。ソーシャルメディアなどで迅速・広範に拡散する誤情...

脳は外界からの情報入力から中枢神経系を経て行動を発現させるまでの情報処理を驚くほどの速さで行っているが、外界の情報は膨大かつ曖昧であり、脳の能力も世界を正確に表現するには絶対的に不足しているように思われる。にもかかわらず...

建築家でもある講師が空間の美をどのように分析しているかについて話す。 講師 川添 善行 先生東京大学 生産技術研究所 准教授 講義:オンデマンド配信 お問い合せ先 本講義に関するご質問等は、「各種お問い合わせフォーム」よ...

音や光などの外部刺激は、耳や目などの感覚器官で神経活動に変換され、知覚経験となる。その際、我々が経験する知覚は、必ずしも外部刺激を正確に反映したものではなく、経験や知識の影響を受ける。講演では、感覚知覚情報処理に関する脳...
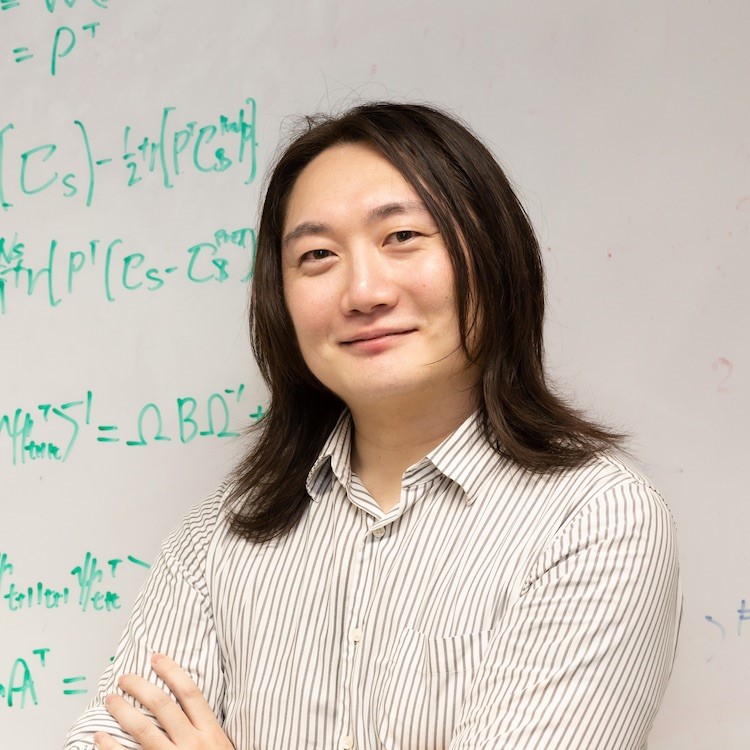
脳を構成する神経細胞は、どのように生物の優れた知能を実現しているのでしょうか?例えば、壁の近くにリンゴがあるとき、私たちはリンゴが壁の形に欠けているとは考えず、リンゴの一部が壁に隠れていると考えます。こうした経験に基づく...

本講義では、「音楽神経科学の社会実装:イヤホン型脳波計を用いたニューロミュージックの研究開発」と題し、音楽と脳波の接点に焦点を当てた先端的な研究とその応用事例を紹介します。まず、耳に装着するだけで日常的に脳波を計測できる...
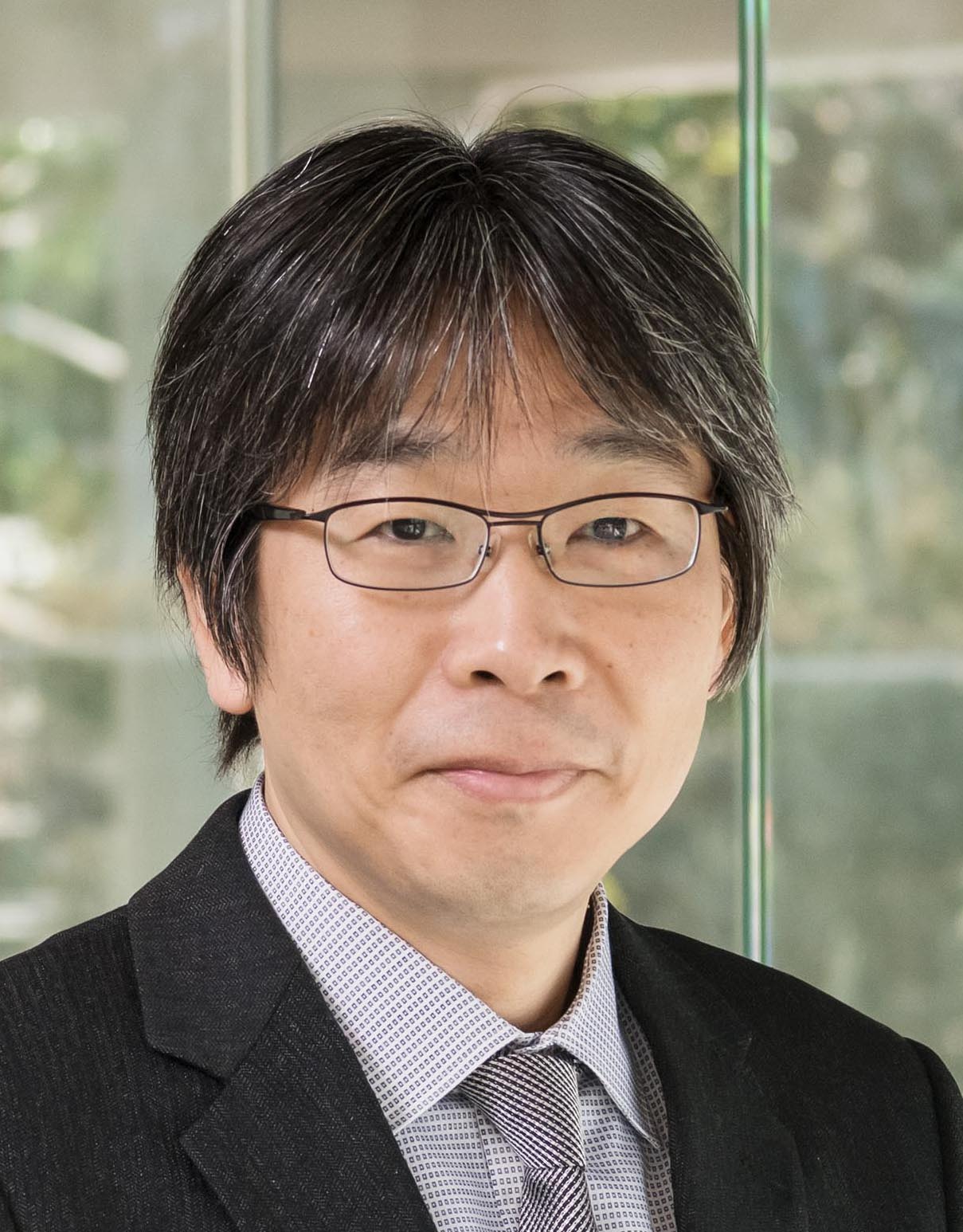
第1回 認知神経科学の分野では、日常場面におけるさまざまな人間の行動を、心理学的側面だけでなく、神経科学的側面を含めて説明する試みがなされており、これまでに非常に多くの成果が得られています。近年は、感情、記憶、意思決定、...
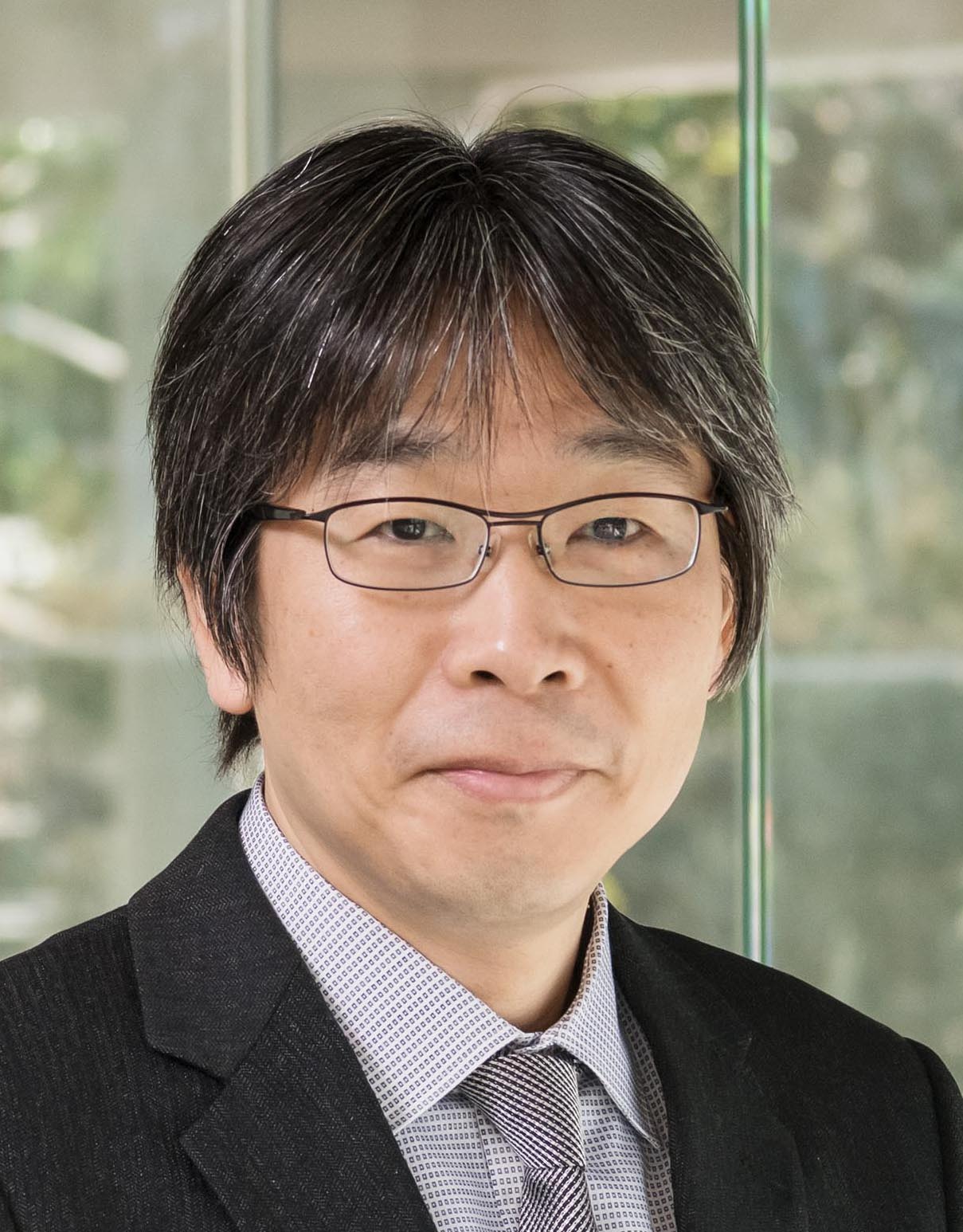
これまで,さまざまな精神症状および神経症状の背後にある神経メカニズムが少しずつ解明されていたが,感情・記憶・社会性といった認知機能の低下や歪みを生じさせる背景として,自律神経活動の状態およびその感知と制御が深く関わってい...

ベイズ的知覚観というものがあります。われわれ人間やその他の生き物は、たとえば網膜のようなセンサーに時々刻々と入力してくる観測データを元にして、それを生み出した外界の状態(たとえば太陽の高さ)という隠れ値を推定する、このよ...

主体性とは一般に「自らの判断と意志とに基づいて対象に働きかけ、目的を実現し、さらにその結果についての責任を負おうとする態度」のことを指すが、脳科学的には、外界や他者と関わる複数の脳機能の総合によって形成される複雑な現象と...