
記憶と潜在意識下の脳機能:井ノ口 馨(富山大学 学術研究部 医学系 卓越教授)
本講義では、脳の情報処理のメカニズムをわかりやすく解説すると同時に、「潜在意識下の脳の活動とその機能に関する最新の研究成果」をお話しします。 睡眠中やリラックスしているときなどに独創的なアイデアなどが出やすいことは昔から...
応用脳科学アカデミー

本講義では、脳の情報処理のメカニズムをわかりやすく解説すると同時に、「潜在意識下の脳の活動とその機能に関する最新の研究成果」をお話しします。 睡眠中やリラックスしているときなどに独創的なアイデアなどが出やすいことは昔から...

精神医学に関連する心理学的研究は疾患の負の側面に焦点を当て、それを是正するような治療アプローチが中心であった。著者自身も、感情や情動といったテーマの認知神経科学的研究を行ってきたが、どちらかと言えば、ネガティブな感情を...
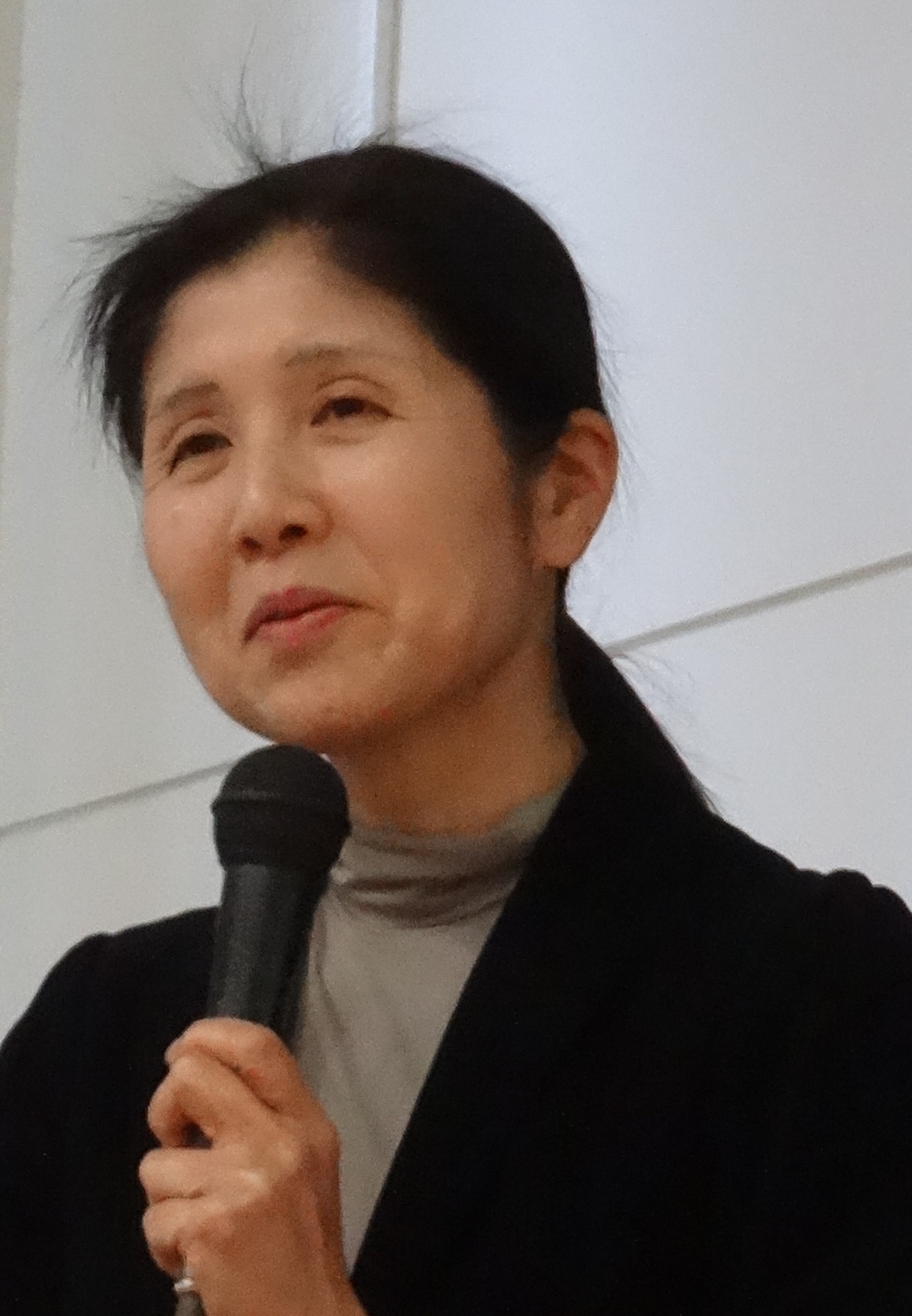
超高齢社会の中で,健康な高齢者の心理・行動的特性を知ることの重要性が増している.それは,1)健康で自立をした生活を営む高齢者との協同やコミュニケーションの頻度が増える中,いかにうまくそうした相互作用を行うか,2)そうした...
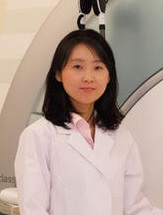
偏ったものの見方や思い込みなどの「認知バイアス(認知の歪み・錯覚)」は、これまで、認知科学、社会心理学、行動経済学において研究が続けられてきました。認知バイアスは、外界の刺激などに対して脳内で独自に創造された「主観的経験...

日本は、今総人口における年齢構成割合の急速な変化の真っ只中にいます。いわゆる超高齢化です。しかし、この変化も2040年以降は収束し、年齢別人口の構造は安定期に突入して、その後100年以上に亘り、年齢構造の変化のない時代が...

サイエンスにおいては、機械に感情を保有させる議論がある。人のような感情は「寿命」「進化」が必要と指摘もあるが、問題はその先である。「作込みの感情でない、内在し、中から生まれ出る」という主張は一理あるが、「偶然生物に感情の...

我々が創造性を発揮できる背景には、どのような認知・神経メカニズムが存在しているのでしょうか?我々の意識や意識下で起こる過程は、創造的なアイデアの生成にどのように貢献しているのでしょうか?これらの疑問へ迫るべく、本講演では...
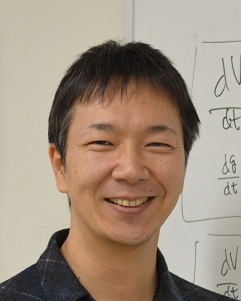
脳は約千億のニューロンがそれぞれ数千のシナプスを介して互いに結合し合う巨大なネットワークである。興味深いことに脳内では、ニューロンの活動とシナプスの変化との両方が、自発性に、しかもランダムに動作することが分かっている。例...

本講義では、リズムを処理する脳の不思議について、皆様と共に、探究してみたいと思います。私自身、ドラマーとしてリズムを演奏します。そのリズム演奏の感覚の中には、宇宙の感覚があります。その感覚を脳科学の観点から眺めてみると...

ダイバーシティは、各々が偏見を持ち合い、バラバラに活動していたのでは、インクルージョンにつながらず、個人や組織のウェルビーイングや潜在能力の発現につながらない。本講義では、高信頼性組織、共同創造、アンチスティグマという...